第二部門/多年にわたる功労
西崎 春吉


西崎さんは、日活のオーディションに合格し俳優を目指していたが、同社の経営悪化で1959年に函館の映画館の宣伝係に転じた。西崎さんは朝から晩まで映画のことを考えていられるのがとにかく嬉しいという程の映画好きで、2003年に亡くなった妻芳子さんとの出会いもこの映画館だった。
函館やその周辺の町で多くの映画館がバタバタと閉鎖されはじめた頃、「バスや列車を何時間も乗り継いで映画を見に行く時代になってしまうのだろうか」と2人で毎日心配していた。1967年、紙芝居からのヒントで思いついた「移動映画館」を夫婦で始めた。借金をして中古の映写機を購入し、使い方を映写技師に教わり、「いどーえいが」と手書きした看板を車に取り付け、機材を積み込み、函館から片道4時間ぐらいで出かけられる映画館の無い町ならどこへでも行った。
月に15日ぐらいの上映が精一杯のところを採算悪化から無理して25日に増やした。夫婦2人で、公民館や公共ホールの会場手配、映画会社からフィルムを借り、ポスターづくりやチラシ配り、宣伝、会場設営、入場料の集金まで全てをこなした。宣伝は上映日の1週間前から行う。ポスターを貼らせてもらい、子ども達にチラシを配る。終わると次の町でのチラシ配り。上映当日は芳子さんが椅子を並べ、ゴザを敷きスクリーンを張っている間に西崎さんが映写機を組みたてた。
現在はこれらすべてを西崎さん一人でこなさなければならない。しかし、子ども達が「おばさんがいなくて大変だから」と進んで椅子の出し入れをしてくれる。上映はアニメが中心で、どの会場でも客は多くて数十人。子どもの数もぐんと減り、2、3人相手に上映することもある。人からは、「もうからないのにバカではないか」と言われるが、上映中の子供達の真剣に映画に見入る様子を映写機の後ろから見ていると「やめたい」と言う気持ちも消える。映画ならではの大迫力、感動の一体感を子ども達に感じてもらいたいと今日も活動を続けている。西崎さんは「みんなの喜ぶ顔が見たい。赤字続きでも楽しみにしている子が一人でもいる限り死ぬまでやめるつもりはない」と語っている。





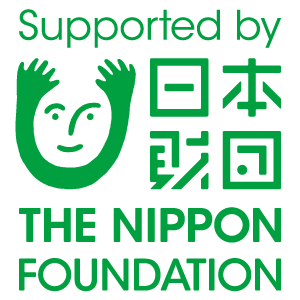
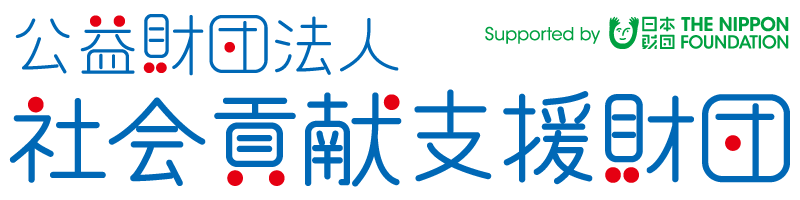


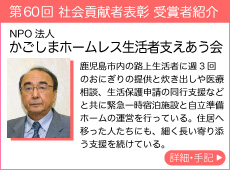

受賞の言葉
この度は、思いがけずこのような素晴らしい賞をいただきありがとうございます。
映画が好きで日々続けてきましたが、いつしか40年近くの時が過ぎていました。食い入るようにスクリーンを見つめる子供たちの顔を見るたび「この仕事を続けて来てよかった」と思っています。命ある限りこの仕事を続け、私が街に来るのを心待ちにしてくれる人たちに、これからも感動を届け続けたいと決意を新たにしているところでございます。