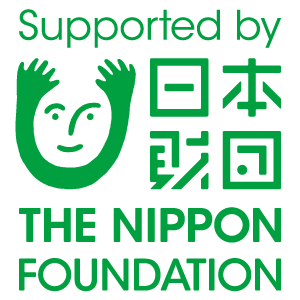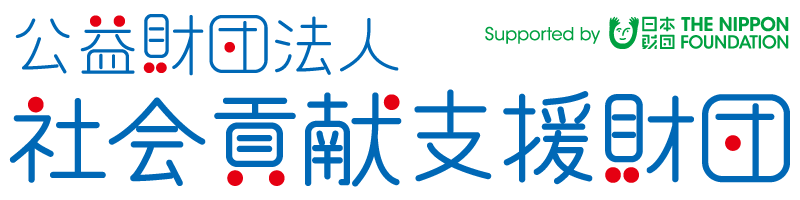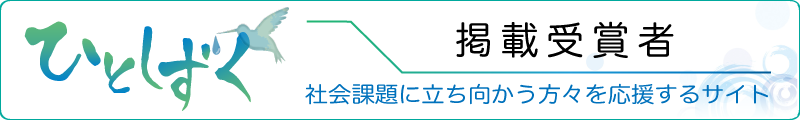窪田 祥吾

小児科医として日本赤十字社や国際赤十字社(ICRC)を通じて難民キャンプや紛争地域で活動、その後JICA専門家としてラオスへ赴任後、2016年よりWHOラオス国事務所に母子保健担当医官として勤務。妊産婦・小児の死亡率を削減し、“Respectful Care”(尊重されたケア)の普及のため、緊急産科ケアなどのトレーニングや保健システムの強化(人材確保、医薬品確保など)を実施。ラオス全国の僻地の村々で参加型ワークショップを行い、村人を支える地方自治体の強化などに努める。新型コロナウイルス感染症の流行に際し、2020年4月ラオスの全国ロックダウン初日から、1 か月半の間に、全国 17ヶ所の県病院で院内感染予防と治療のトレーニングを実施し感染防御と治療を行う。コロナ禍にあっても必要となる妊婦健診や出産、小児健診、内科外来といった保健サービスを保持するための活動も行う。ラオ語にも精通し、医療関係者や政府関係者からの信頼も厚い。天文物理学を経て仏教人類学を専攻した後に医学部へ編入学。病気で亡くなる人の幸せな最期を迎えるための準備の場を作りたいと医師や助産師やダンサーと共に五感を使った『いのちの教室』を開催するNPO「こころっコロ」(生と死を考える団体)を設立した。コンテンポラリーダンスのダンサーとしても活躍し、宗教、人類学、 医療といった経歴を活かし国際保健に貢献している。
高校時代にタイへ留学、仏教寺院で出家、米国大学で宗教人類学を学んだ後、一人一人が自分らしく生きていけるようなサポートを出来るようになりたいという思いで、医学の道へ進みました。ところが日本の医療体制は、特に最期を迎える人やその家族にとって、最期までその人らしい生き方が出来るようなサポートが出来ているように感じられませんでした。そこで一人一人、その人らしい最期を過ごせるように何か出来ないかと、同じ想いを持った仲間を集い、活動を始めました。一般の人々とは市民講座などを通じて、家族内でどのような最期を過ごしたいかを話し合っておく大切さやそういった機会の作り方などについて話し合いました。小学生とは参観日などを通じて、終末期医療で直面する困難な選択などについて話し合ってもらい、「死」に対する自分の思いや他の人の考えに触れる機会を作りました。また親にその姿を見てもらうことで、子どもが生や死に関する話題を出した際には、避ける事なく自然に話せる環境を作ってあげることの大切さやその方法について考えてもらいました。しかし、日本においては医療者、特に医師の説明の仕方が大きく治療方針の意思決定に影響をするという事が分かり、医学生への働きかけもしました。全国様々な大学で医学部を中心に授業を行い、自分や近しい人の理想的な最期を思い描いてもらい、医療者側として出来ることを考えてもらいました。
臨床医時代はこのようなボランティア活動や人道支援に関わっていましたが、その後JICAを経て、世界保健機関でラオスの公衆衛生に携わるようになりました。今年でラオス在住11年目になります。主に中央保健省や病院における援助をして来ましたが、新型コロナ感染症蔓延を期に、保健セクターを越えて、より住民が主体となった活動に重きを置くようになりました。ラオスは人口700万人強という小さな国ですが、50の民族が存在し、言葉も慣習も様々です。各々の村、村人にとっての「健康」の在り方を模索することを横からサポート出来るような働き方を目指して、医療者のみならず人類学者や社会学者など様々な人々と協力しながら活動しております。
臨床の場であれ、公衆衛生であれ、今後も一人一人がその人らしく生きていけるような世界を目指して自分なりに出来る事をしていければと思っています。