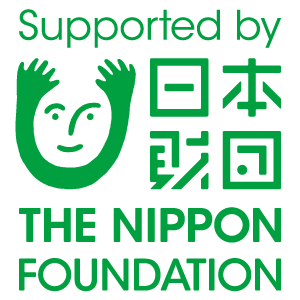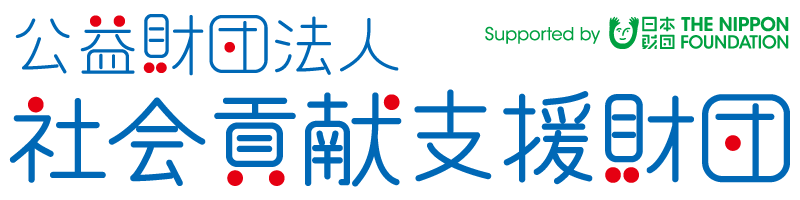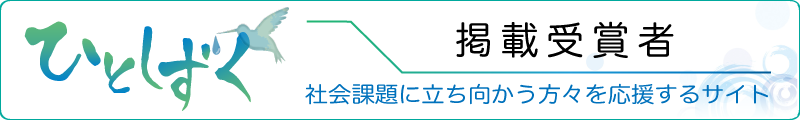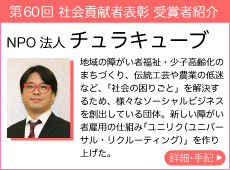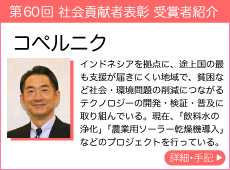森林塾青水

「飲水思源(水を飲むときは、その源を思うべし)」を合言葉に、首都圏で環境保全ボランティアを行っている団体。2004年から群馬県みなかみ町上ノ原茅場で40年ぶりの「野焼」を復活させ、草原を守る活動を行っている。上ノ原茅場はかつて200haにもおよぶ草原あったが、開発により10ha程に激減した。その後、町有地を借り受けるなどで現在は21ha程に戻りつつある。地域と共に協力して茅場を再生し、草原として維持管理している。ここで刈り取られた茅は文化財を中心とした茅葺屋根の材料として使われており、3千束から多い時期は約6千束を出荷している。茅場だけでなく、入会慣行※1という先人の知恵に学び、日本型のコモンズ※2作りに挑戦している。また、生物多様性の保全のため希少生物の保護や環境学習、エコツーリズムなど毎月各種イベントを行っており、活動開始から20周年を迎えた今、上ノ原茅場を環境教育の場としても積極的に利用し、環境省の「自然共生サイト※3」への認定を目標に活動を続ける。
※2コモンズ:地域住民にとって、必要な物を、地域住民で維持管理し、地域住民で利用 するシステムとその対象となる空間
※3民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている地域
活動を始めて今年で20年という節目に、このような栄誉ある賞をいただき感謝しております。森林塾青水は、利根川の水源地である群馬県みなかみ町にある上ノ原という茅場(ススキ草原)を流域の都市住民、地域住民、行政と連携し保全活動を行っております。かつての日本の里山は、主に薪炭林としての雑木林と草をとるための茅場(ススキ草原)がセットで存在していました。このススキ草原の明るく開放感のある風景は、古来より日本人の心の原風景としてDNAに刻まれており、万葉集にもススキを読んだ句が多く残っています。また、童謡のふるさとの歌詞にある「うさぎ追いし かの山」もススキ草原の情景を歌っています。しかし、戦後のエネルギー革命により、田畑を耕す牛馬からトラクターになり、草の堆肥から化学肥料に代わり、茅葺屋もトタンの屋根に変わってしまいました。そのためススキ草原の必要性がなくなり、国の拡大造林の政策もあり、ススキ草原のほぼすべては、スギやヒノキの人工林へと変わってしまいました。
しかし、明るいススキ草原にしか生息できない動植物もたくさんおり、その数も急激に失われていきました。近年、世界中で生物の多様性が急速に失われており、その損失を食い止めるための取り組みが、世界の共通の目標としてネイチャーポジティブと呼ばれています。我々が活動を始めた20年前には、このような世界になるとは想像もしていませんでしたが、それだけ地球の環境が悪化していることの裏返しでもあるといえます。
我々の管理する上ノ原のススキ草原は、わずか10haの小さな点ではありますが、絶滅危惧種も多く生息しています。また、関東一円の文化財の屋根材としてもススキを供給しており、文化庁が指定する文化財の森にも認定されています。これからも、生物の多様性の保全や日本文化の継承に寄与できるよう活動を続けて行ければと思っています。
上ノ原の茅場は誰でも訪れることができますので、ぜひ日本の原風景を見に来ていただければと思います。また、我々と一緒に活動してもらえる仲間も募集中です。春の野焼きに始まり、山菜採り、防火帯の刈払い、間伐作業、茅刈りなど通年、だれでも参加できる活動も定期的に開催しておりますので、お気軽にお問い合わせください。