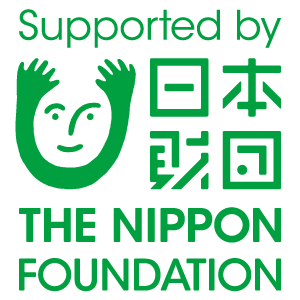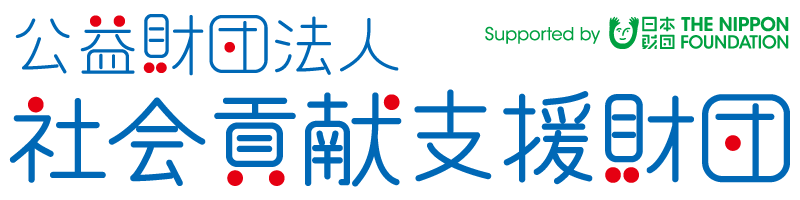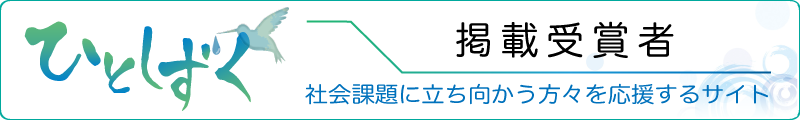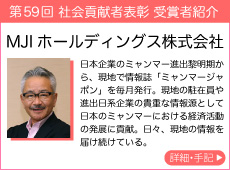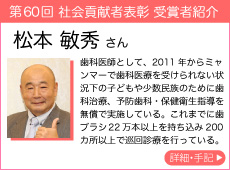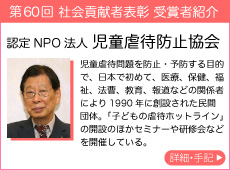NPO法人 アーシャ=アジアの農民と歩む会

「アジア諸国の農村住民に対して、地位の向上と自立を促進するために、人権、貧困、環境、福祉等に関する農村開発支援事業、及び災害、紛争などによる被災住民への緊急支援活動を行い、これによって人間の尊厳を尊重する社会の形成に寄与すること(定款より)」を目的とするNPO法人。40余年前、北インド・ウッタルプラデシュ州アラハバード(現プラヤグラージ)の農業大学(現サムヒギンボトム農工科学大学)に招かれた牧野一穂さんは、小規模農民の生活水準が低迷し、貧富の格差、女性や弱者への人権軽視、根強く残るカーストの問題により、困難な生活を余儀なくされている人々を支援するために継続教育学部(マキノスクール)を設置した。2004年、牧野さん退任に際し、後継者として三浦照男さんが赴任するにあたり、これまでの活動を継続、さらに発展させることができるよう、また「貧しい農村の人々の希望の光となるような活動を」との願いをこめて、NPO法人を設立し「アーシャ(ヒンディー語で希望)=アジアの農民と歩む会」と名付けた。現在は、マキノスクールと協働で、環境保全に配慮した持続可能な有機農業の普及、貧困家庭の子ども・女性の教育支援、農村開発リーダーの育成、母子保健活動の実施、女性の社会的・経済的地位向上を目指し、縫製技術やマーケティング支援など、総合的な農村の発展を目指し、住民が自ら個々の問題を解決できるように、特に人材の育成に力を入れて支援を行っている。
この度は、栄誉ある社会貢献者表彰を賜りまして、誠にありがとうございます。
北インド、ウッタルプラデシュ州プラヤグラージ県で活動中の日本人スタッフ・現地スタッフ、また、日本でその活動を支援しているみんなで喜びを分かち合いました。
心より感謝申し上げます。
私たちは、アジア諸国の農村住民に対して、農村の草の根で働く人材育成を軸として、人権、貧困、環境、福祉等に関する農村開発支援事業及び災害、紛争などによる被災住民への緊急支援活動等行ってきました。これらの活動を通して人間の尊厳を尊重する社会の形成に寄与することを目標に、2004年にNPO法人 アーシャ=アジアの農民と歩む会を発足させました。
アーシャとは、ヒンディー語で「希望」を意味します。
20年間の歩みには、カウンターパートのマキノスクール(サムヒギンボトム農工科学大学継続教育学部)を通して、小規模農民の食料生産の安定、環境保全に配慮した農業を目指すAOAC(アラハバード有機農業組合)の設立支援、「持続可能な農業・農村開発コース」運営支援、プラヤグラージ県の農村女性の収入向上、社会的・経済的地位の向上、能力開発、エンパワーメントなどを目指したAVSS(アーシャ開発奉仕協会)の設立支援など幅広い活動を行ってまいりました。
表彰式が行われた7月、現地では、ミャンマーや北東インドからの研修生がマキノスクールに集い、「持続可能な農業・農村開発コース」が始まった時でした。内紛や軍事政権下での農村を守ることはとても困難なことですが、希望をもって学んでいる姿に心打たれます。
彼らの学びを今後も継続して支援できるようにと願っております。
また、北インド農村女性の地域や、家族における地位は低く、高等教育を受けられない女性もまだ多く、男性や他の地域の女性に比べると、ウッタルプラデシュ州の女性の識字率は低いとされています。女性たちが手に職をつけ、収入を得ることがこれらの問題を解決する一助となりますから、今後ともAVSS(アーシャ開発奉仕協会)を通して、農村女性支援を継続してまいります。
20年間の歩みを通し、まだ多くの課題が残されておりますが、今回の受賞を励みとし、今後とも、より多くの方々に、「アーシャ」の活動を知っていただき、支援の輪が広がるように努力し、活動を継続していく所存です。
改めまして、この度は、大変ありがとうございました。
 育成した農村保健ボランティアと日本から届いた毛糸のおっぱいと記念写真(母乳育児教育教材)前列左端 三浦代表
育成した農村保健ボランティアと日本から届いた毛糸のおっぱいと記念写真(母乳育児教育教材)前列左端 三浦代表 モリンガ葉の選別作業を行う農村女性たち
モリンガ葉の選別作業を行う農村女性たち アーシャが支援するマエダ村のアーシャ小学校の子どもたちと校長先生(オレンジのサリーの女性)
アーシャが支援するマエダ村のアーシャ小学校の子どもたちと校長先生(オレンジのサリーの女性) 現地統括責任者三浦照男と農村開発コースの研修生。マキノスクール有機農場にて
現地統括責任者三浦照男と農村開発コースの研修生。マキノスクール有機農場にて 豆腐製造を学ぶ農村開発コース学生たち
豆腐製造を学ぶ農村開発コース学生たち 保健ボランティアによる農村での栄養教室(料理講習試食会)風景
保健ボランティアによる農村での栄養教室(料理講習試食会)風景 保健ボランティアによる農村での身体測定調査
保健ボランティアによる農村での身体測定調査 縫製工房の女性たちと新作ヨガパンツを手に(右端、スタッフ川口景子)
縫製工房の女性たちと新作ヨガパンツを手に(右端、スタッフ川口景子) 有機米の栽培セミナーにて質問をする有機農業組合員たち
有機米の栽培セミナーにて質問をする有機農業組合員たち 2023年度農村開発コース(9か月)入学式風景
2023年度農村開発コース(9か月)入学式風景